読む
2023.02.27 住職のおすすめ本
アジア人物史 [17~19世紀] アジアのかたちの完成 集英社2022
![アジア人物史 [17~19世紀] アジアのかたちの完成 集英社2022](https://tentoku-ji.com/wp/wp-content/uploads/2023/02/DSCF5559.jpg)
江戸時代、朝鮮半島から日本へは、朝鮮通信使という友好使節が来ていた。そのように歴史の教科書では習った。このことにはいままでなにも気にしていなかった。
けれども考えてみれば、江戸時代以前、日本は朝鮮半島に攻め入り、軍事的侵略をしていたのである。言うまでもなく、秀吉の朝鮮出兵である。
そうであれば、日本は、朝鮮半島に対して軍事侵略を行い、そののちに国交を回復し、通信使を送ってもらうまでになったということだ。そのような国交の回復がどのように行われたのかについて(そしていったん国交が回復した両国の関係が、またも明治日本の軍事侵略をどのように志向させたかについて)、私はいままでなんの想像もしてこなかった。文字通り「無関心」だったのである。
けれども、この国交回復には対馬藩の苦闘があったということを、このたびの本の木村直也「江戸時代の日朝関係とその変容―対馬の動向を中心に」ではじめて知った。はずかしいことである。
現在、朝鮮半島と日本との関係は最悪であり、それは日本が軍事侵略を行い、徴用工動員などを行った、加害者としての行為に対して、国として清算できていない多くの部分があることに原因の一班がある。
かつて江戸時代に、対馬一藩に課せられた朝鮮日本両地方間の調整の機能は、近代国家どうしの交渉におきかえられ、それは世界情勢全体のパワーバランスともつながって、きわめて複雑になった。この状況をどう解きほぐすかは、けれどもやはり、まずは歴史を参照することからはじめるべきであり、対馬藩の苦悩をより詳細に見る必要があると思う。
本書はほかにも、前田舟子「琉球王国の新時代」、川原秀城「朝鮮実学」、小松久男「中央アジアの十九世紀」など、いままで「無関心」であった領域をするどく衝いた問題を詳述して、現在の複雑な国際関係の淵源を照らし出している。本書を読み、私はなんども驚嘆した。シリーズの続巻も刮目して待ちたい。
2022.01.25 住職のおすすめ本
「戦士の休息」 岩波書店
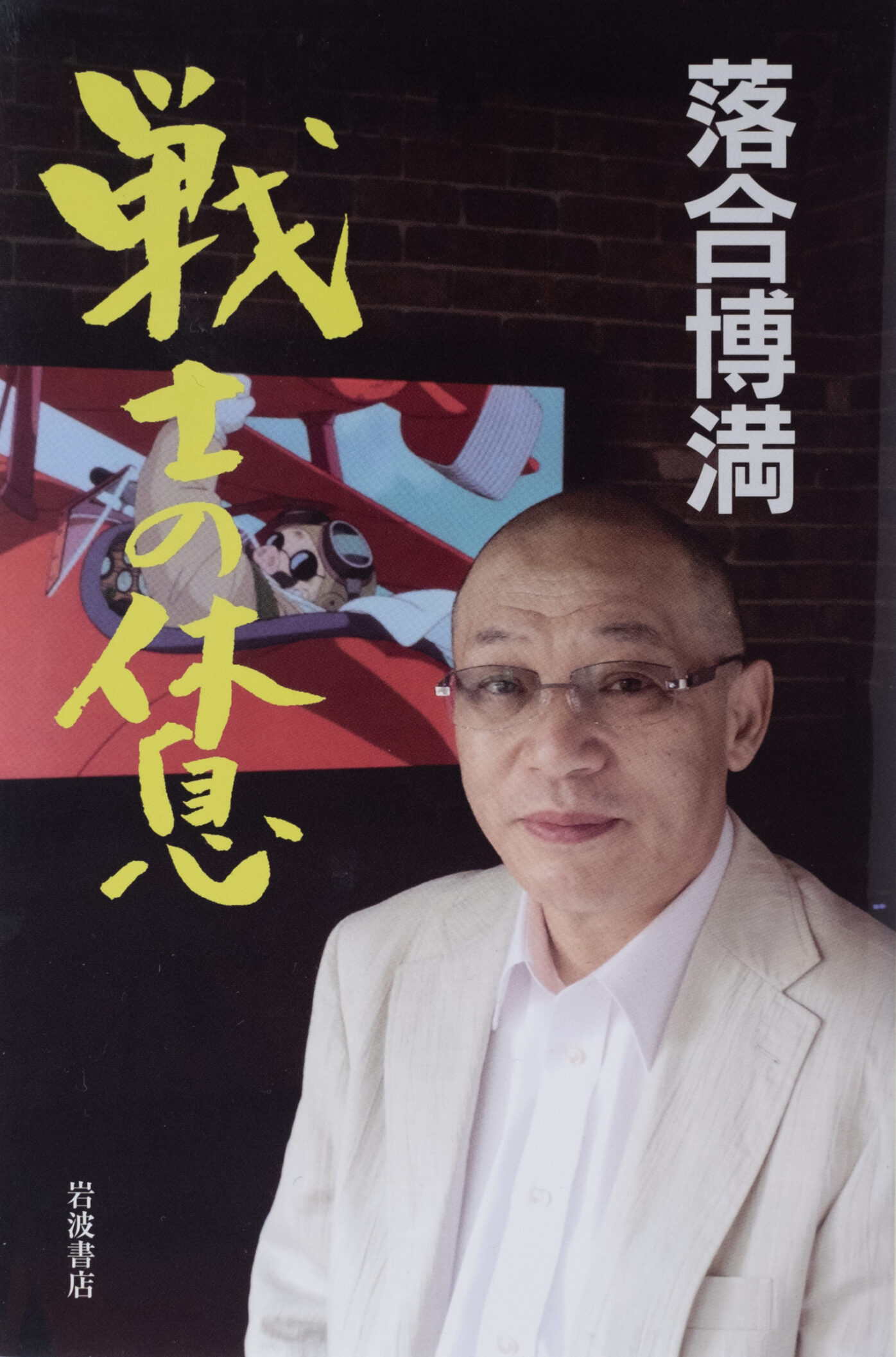
落合博満氏が、いまもっとも気になる人である。落合氏とは、ご承知のように、プロ野球選手としてはロッテ・中日・巨人・日ハムと渡り歩き、3度の三冠王を取り、プロ野球監督としては中日を率いた8年間にリーグ優勝4度、日本一1度を達成した人物である。だが選手のときにも、監督の時にも、活躍しているその時には、実は興味がわかなかった。それが最近になって妙に気になる人物となり、本や発言などを漁るようになった。
『戦士の休息』は落合氏が映画について書いた本で、もとは氏の趣味である映画鑑賞に目をつけたスタジオ・ジブリの鈴木敏夫プロデューサーがジブリの会報『熱風』に依頼した連載である。プロ野球界についての氏自身の深い見解や分析と、年季の入った映画鑑賞眼とが交錯して、唯一無二の読み物となっている。一方『嫌われた監督』は、元中日新聞の落合番の記者によって書かれた落合氏の監督8年間についてのドキュメントであり、氏の一見突飛にみえる言動の理由を丁寧に解き明かし、深く考えさせる読み物となっている。
落合氏は、歯に衣着せず、率直な発言をする。それは時に大言壮語、有言実行といわれた。かと思うと監督時代には、マスコミや選手に沈黙を守り、語るときにはポツリと預言のような謎めいた言葉を残し、試合中には無表情を貫いた。そしてそのどちらにおいても、周囲を驚かせる決断をして結果を残した。この率直と決断、秘密と即断の根底には、「プロフェッショナルとして、何が求められ、そのためにどうしなければならないか」という根底的な認識があったのである。
一見奇矯なその言動が、実は誰よりもものごとの基本にもどり、それを自分ながらに考察することによって考え抜かれたうえで発せられていることが、両書をあわせよむとよくわかる。落合氏の言動はものごとの本質をつねに新鮮に衝く。それもまた、基本に忠実に、シンプルに考えているためである。そのシンプルさが、無駄なことがらをうろうろ考えてしまう私たちにとって、かえって新鮮に、斬新に響くだけなのだ。局所局所に、私たちがそれぞれ個として生きる根本を見直す場合に、氏の言葉と行動は、大きな勇気を与えてくれる。
2021.09.01 住職のおすすめ本
「菌の声を聴け」 ミシマ社
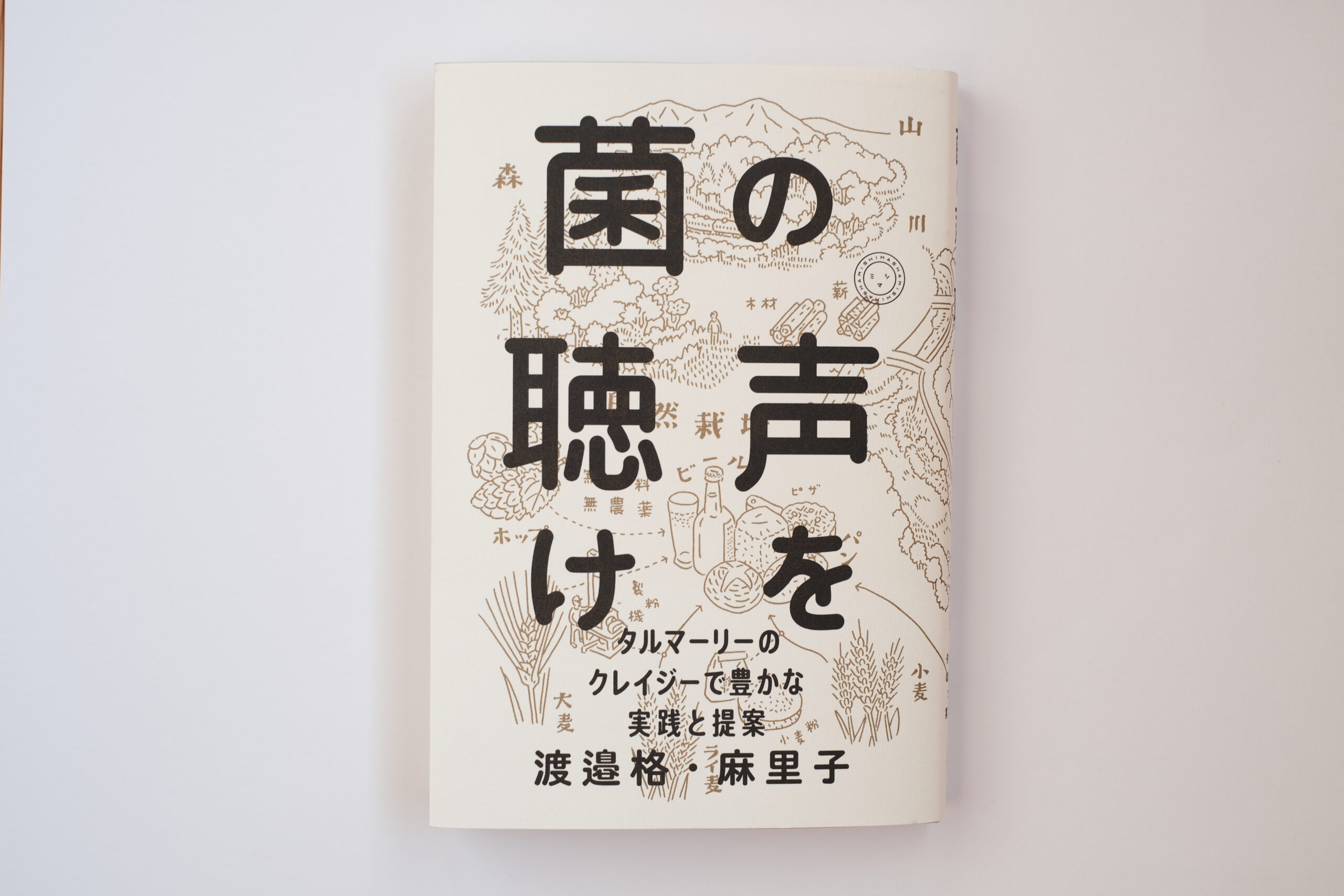
「菌の声を聴け」ミシマ社
渡邉 格・麻里子 著
こんな話がある。ある老僧が言った。「虚空を掴むことを知っているかい」僧が応える。「知ってますとも」「やってごらん」僧は手で空中を掴む動作をした。老僧「ああ、おまえはやっぱりわかってない」僧「じゃあ、どうやって掴むのですか」老僧は突然、僧の鼻をつまんで力任せに引っ張った。「いたたたた!鼻が取れてしまうじゃないですか!」老僧「そうそう、そうやって掴むのだ」。道元禅師の『正法眼蔵』「虚空」巻に見える話である。
渡邉夫妻の近著である『菌の声を聴け』を読んで、しきりにこの話を思い出した。夫妻は鳥取県智頭町で、野生の菌で発酵させてパン・ビールを作るお店「タルマーリー」を経営している。本書はパンとビールを作る過程を描きながら、夫妻自身の人生の反省と再生譚とも、会社の移転成功譚とも、社会変革の提案実践とも読める多視角的な本となっていて、非常に面白い。私は特にこの本を、「菌活」(渡邉氏の造語)という実践に根差した、一種の仏教的実践書として読んだ。
たとえば次の箇所。「野生の菌による発酵は曖昧で動的だ。・・・動的なモノ作りにおいて職人は、日々現象を観察して経験を蓄積し、全体の関係性の中から直観的に最適解を導いていく。・・・すると職人は、大事な素材と一体化して作るモノを自分の分身みたいに感じるようになる」(86~87頁)。野生の菌を降ろして発酵を行おうとする場合、菌と職人というバラバラの個別なものの足し算ではなく、すべてがつながった大きな全体的環境のなかで、環境の一部としての菌を、環境の一部である職人が扱うという状況に自覚せざるを得ない。このことは結果として、職人自身をも含まれる全体の一部として、自分自身としての発酵を扱うということになる、というのである。さきほどの「虚空を掴む」話では、虚空とはさとりのことだが、僧は虚空を、自分とは別の、掴むことができる対象だと思っていた。しかし、虚空=さとりとは、僧自身をも含む世界全体のことであって、虚空を掴む(さとりを開く)とは、全体とのつながりのなかで存在する自分を掴むことだ。だから老僧は、自分自身を動的に、実践的にとらえてこそ、「虚空を掴む」としれ、と言ったのである。この逸話はそうした意味で、渡邉夫妻の発酵の実践(「菌活」)と照らしあう話であるように思っている。
本書ではまた、「発酵を取り巻く環境は、単純な「因果」ではなく、複雑な「縁起」で捉えるべき世界だろうと思う」(85~86頁)とも言われ、『般若経』の「空(くう)」の教えや、「禅」の修行の要諦と照応する言葉も見える(巻末の参照文献では仏教学者梶山雄一氏の本も見えている)。こうした仏教と照応する知見が、モノづくり、地方からの生活スタイルの見直しに直結しているのを見るのは新鮮な驚きである。実は渡邉さんのお子さんは、智頭の森のようちえん「まるたんぼう」で私の息子の二年上のお兄さんだった。「タルマーリー」のチーズのパンが好みで、一家でよく食べている。お近くに優れた理論家=実践家がいらっしゃることはとてもたのもしい。
2021.07.01 住職のおすすめ本
「子どもの話にどんな返事をしてますか?」 草思社
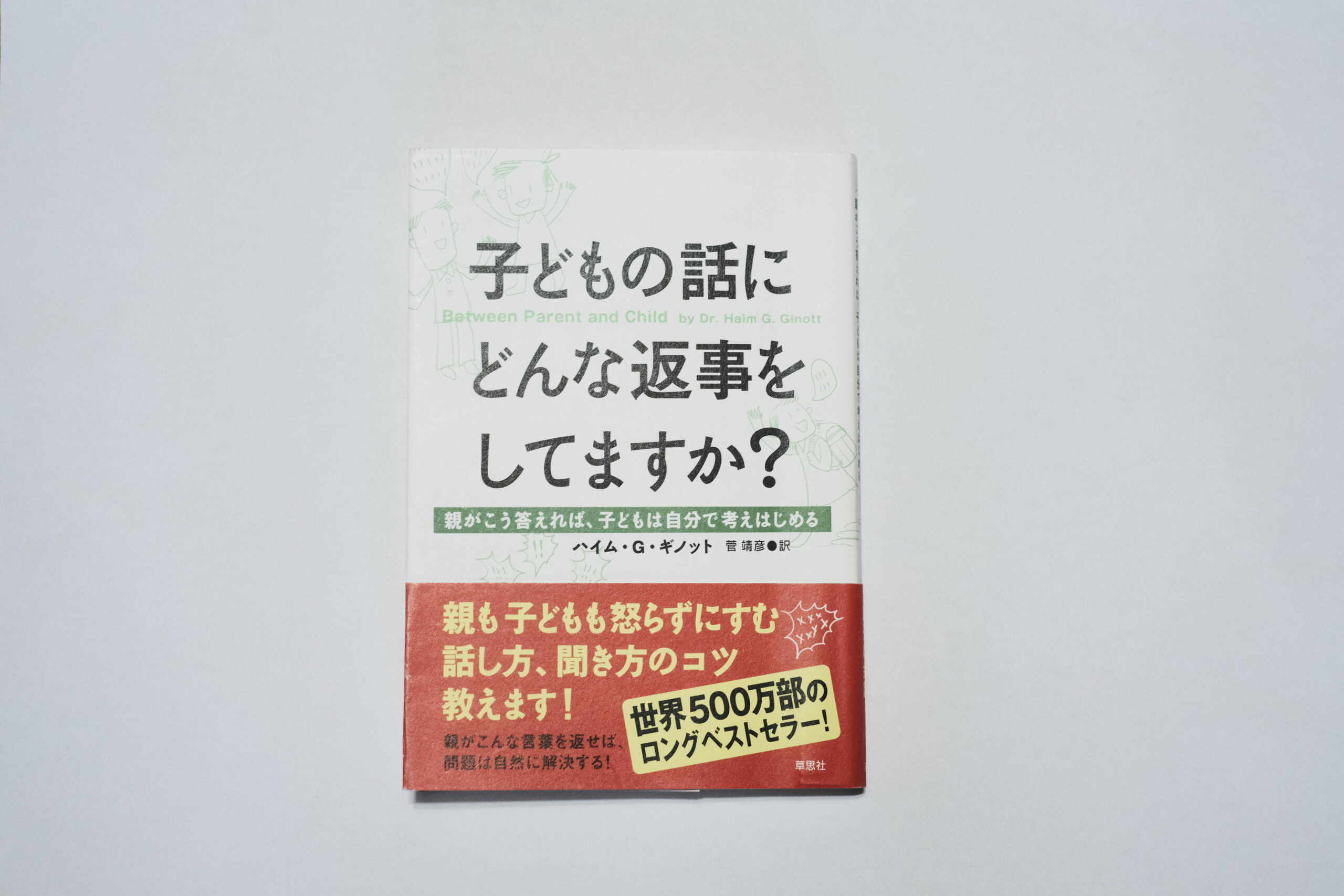
「子どもの話にどんな返事をしてますか?」 草思社
ハイム・G・ギノット 菅 靖彦訳
子育てはつくづく難しい。子どもは、こちらが思うようには決してなってはくれず、すねるし、怒るし、泣くし、あばれる。どうやってコントロールしようかと考える親の思いを常に裏切ってゆく。今、問題になっている多くの虐待事件や、親への暴力事件は、そもそもこうした親子間の日々のすれちがいが積み重なってエスカレートしてきたもののように思える。それは、親と子どもの双方に大きな負担を強いる。ではそのような、双方に不幸をもたらすすれ違いが起こらないようにするにはどうすればよいか。本書を読んで、わたしは大げさでなく、子どもへの言葉の使い方が180度変わった。
本書は「はじめに」で、次のように言う。「子どもを傷つけるような対応の仕方をするのは底意地の悪い親だけだとわたしたちは思いがちである。だが、不幸なことに、そうではない。愛情豊かで、善意の心をもった親も、責める、辱める、非難する、あざける、脅す、金品で買収する、レッテルを貼る、罰する、説教する、道徳をおしつける、ということをひんぱんにしている。なぜだろう?たいていの親は、言葉がもつ破壊的な力に気づいていないからだ。親たちは、気づくと、自分が親から言われたことを子どもたちに言っている。自分の嫌いな口調で、言うつもりのなかったことを言っているのだ。
そのようなコミュニケーションの悲劇は、思いやりに欠けているからではなく、理解不足に起因していることが多い。親は子どもたちとのかかわりで、特別なコミュニケーションのスキルを必要とする」。この箇所を読んで、ギクッとしない親は、多分いないだろう。それぞれ多かれ少なかれ思い当たるところがあるからだ。
では、このような悲劇に陥らないコミュニケーションのスキルを、どのように身につければよいか。親たちはともすれば、子どものふるまいとともに、その気持ちも批判し、制限してしまおうとする。しかし、私たちもそうだが、子どもの気持ちは、外から強制的に変えられるようなものではないのだ。ふるまいと共に気持ちまで批判すれば、子どもたちは「自分はわかってもらえていない」と思うだけだろう。だから、気持ちは全面的に受け止め、行為だけはその場面に応じて制限をかける、という、寛容さと冷静さとが親には必要なのだ。さらに、それは抽象的な机上の教育論としてではなく、子どもに言葉をかけるときに、カッとなって批判したり、詰問したり、皮肉を言ったりことのかわりに、気持ちを全面的に受け止める言葉と、彼らの行為を明確に制限する言葉を発するようにするという、実践の問題としてあるのである。ここにスキルが必要なのである。
本書には、実際の場面における話し方の実例が多数挙げられ、読むことで自然とスキルが上げられるように工夫されている。子どもに対するこのコミュニケーションのスキルは、どのような世代の人々に対しても有効であり、私たちは本書を読むことによって、いわば対人関係の基礎スキルを学ぶことができるわけなのだ。育児に悩むご家庭のみならず、あらゆる世代に強くおすすめする本である。
