読む
2025.01.30 お悩み相談
【質問】「老い」との向き合い方を教えてください
【質問】
最近、目は悪くなるし、足腰も弱くなってきたなぁと感じることが増えました。年を重ねることが嬉しい年齢でもなく、老いていく自分に対して前向きに捉えることができません。いずれ人は死ぬということもわかりますが、日々いろんなことができなくなっていくことを、どのように考えたら良いでしょうか。
【回答】
ご質問ありがとうございます。なるほど、老いてゆく自分に対して前向きになれないということですね。若い頃と比較して、つぎつぎといろいろなことが出来なくなる、能力が低下していく自分のありようが憂鬱だ、ということですね。私も今年になって目がひどく疲れ、困るようになりました。若い頃はもっとよく見えて、本も楽に読めたのに、ああ、と思います。お気持ち、非常によくわかります。
これは非常に難問で、どうお答えすればよいか、正直私にはわかりませんでした。そんなときに、中大輔『生きとってもしゃーないと、つぶやく96歳のばあちゃんを大笑いさせたお医者さん』(ユサブル2024)という本をたまたま手に取りました。これは、自身もがんを経験された船戸崇史さんというお医者さんが地域医療で、多くのがん患者を診ておられるありようを取材した本なのですが、そこで船戸医師は「睡眠・食事・加温・運動・笑い」を「がんに克つ五か条」として提唱し、自身も実践されています。しかし、取材された中さんが衝撃を受けたのは、このような「五か条」を唱えて多くの患者さんを診ている船戸さんがいっぽうではつぎのように言われた言葉に対してでした。「がん患者さんはよく„生きるか死ぬか”と考えます。でも考えてみてください。これはおかしな選択です。確かに、かんが治らなかったら死にます。でも、がんが治ってもいずれ死にます。人間は絶対に死ぬんです。死ななかった人は歴史上ひとりもいません。死亡率は100%です。だから„生きるか死ぬか”なんて選択はない。あるとしたら„どう生きるか”という選択しかないんです」。船戸医師が言われているのは、„生か死か”という選択は頭で考え出した偽の選択にすぎず、実際にあるのは、生と死とをどちらも含んだ„どう生きるか”という一択しかないということです。
この船戸医師の言葉はたいへんヒントになりました。私たちは、「若い」ときと「老いた」ときを比較してあれこれ思い悩むのですが、「若い」頃の自分が存在するのは思いの中だけで、比較対象は実際には存在しないのです。だから「若い」ときと「老いた」ときとを比較しても現実的な意味はありません。実際にあるのはこの「現在」だけであり、さらに、「現在」においては、私は最も「若く」「全盛期」を迎えていることになります(これからの自分の体力も知力と比較をすれば、現在が最も若く、元気で、強いことになるからです)。となれば「老い」とは、毎日毎日自己の「全盛期」を迎え続ける時期だといえます。毎日自分の「全盛期」を迎える日々と考えて、現在をわくわくと過ごしていきましょう。
2025.01.30 住職のおすすめ本
岡﨑乾二郎『感覚のエデン』 (亜紀書房2022)
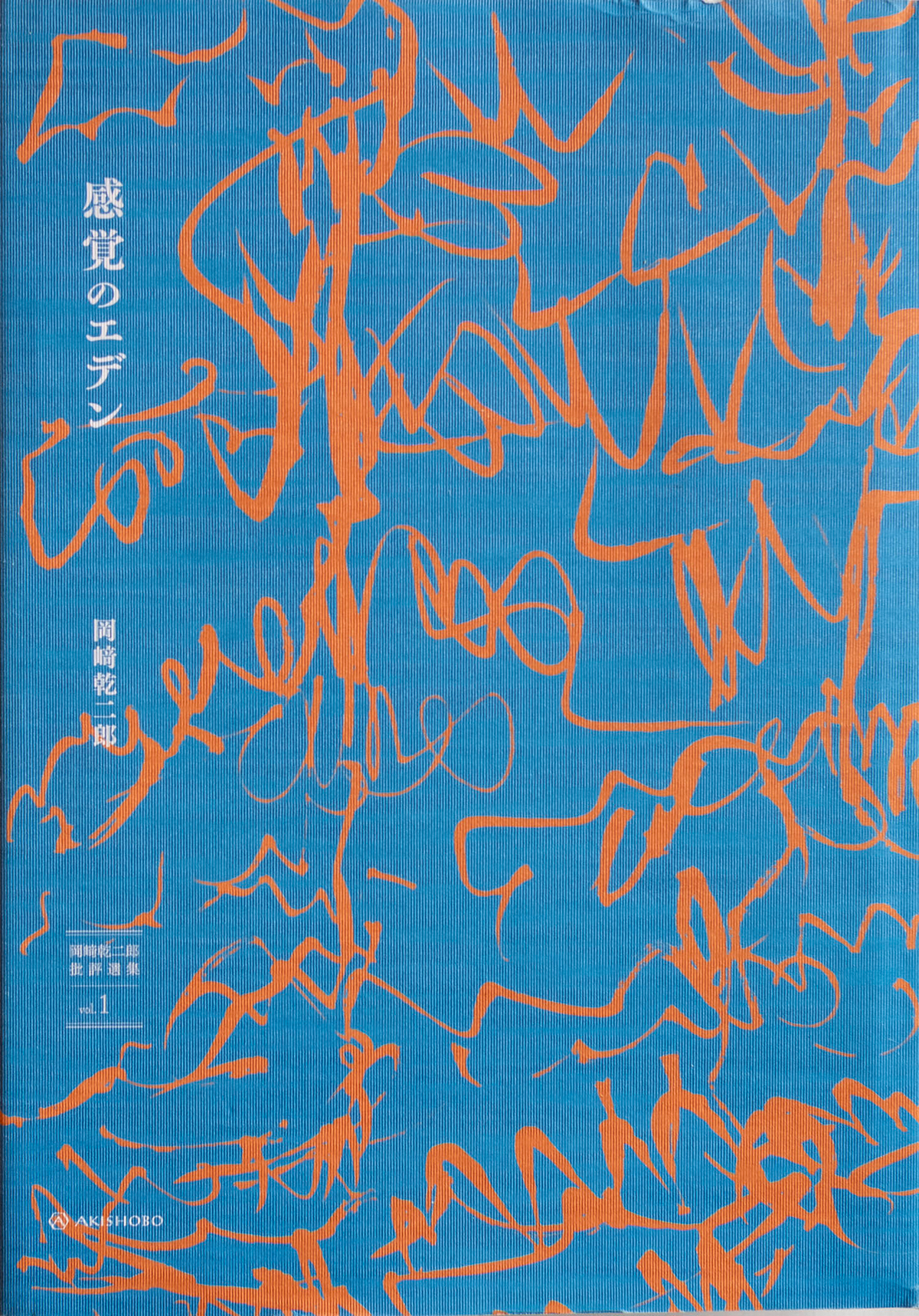
講義のために資料を集め、本をいろいろ読んでいくと、論証や知識が増えていくその一方で、一冊の本が持つ力を、だんだん感じられなくなっていく気がする。一冊の本には言葉を換え、思考を替え、生き方を変える力が、確実にある。だから読書という行為が二千年来成り立つわけなのだが、本を数多くわたり読んでいくうちに、一冊一冊にそんな力が存在していることに対して鈍感になってしまうような気持ちになるのだ。そんなとき、私は岡﨑乾二郎氏の本を開くことにしている。岡﨑氏の本は、発見に満ちている。なによりも、言葉を換え、思考を替える衝撃を、一行一行が持っていて、読むと頭の奥の方に火がつけられ、沸騰をはじめている。
最初の単行本となった『ルネサンス 経験の条件』(筑摩書房 のち文藝ライブラリー)からすでに持っている岡﨑氏のこうした文章の特色を、批評家浅田彰氏はつぎのように讃えている。「(本書は)素早く脳内に入り込むと爆弾のように破裂して悦ばしい驚きと混乱で満たし、交換台のように機能して無数の異質な情報から新しい世界像を紡ぎ出す」。これは岡﨑氏の『抽象の力』(亜紀書房)についての批評だが、岡﨑氏の文章全般にわたっても該当すると思う。本書『感覚のエデン』は、岡﨑氏が折々に書いた論考をまとめたもので、それぞれが極めて貴重な論証であるとともに提言となってもいる。
私たちがこの本を十分に読むには、その時代背景や掲載の場所を参照しておくほうがいいだろうと思う。けれども同時に、時代背景や掲載場所を外して読まれたときに、岡﨑氏の文章は新たな意味を荷い、新たな知性を沸騰させる。たとえば本書に収められる「確率論的主体論」や「理性の有効期限」は、東日本大震災を踏まえて述べられた論述だが、これはまさに能登の大地震に遭い、コロナ禍が残存し続ける現代において、さらにはこれからの未来においても、くりかえし精読されなければならない論考だといえる。新しい世界像は、異なる時代に読まれるそのつど、つねに新しく紡ぎ出されるのだ。おそらくそうした著作こそを、「古典」と呼ぶのである。本書は出版されたはじめからすでに、「古典」となっていると思う。
2024.12.10 台所手帖
私は、必ずしも美味しい料理が作れるわけではない、と気が付いた!ということ

少しショッキングなサブタイトルから始まります。うすうす気が付いていましたが、ついにしっかりと自覚してしまいました。私は、美味しいお料理を作ることができるわけではないということに。
子どもたちのお母さん達との交流は様々な気付きを与えてくれるので刺激的です。大きな学びの扉が開きます。今回はあまりに根源的過ぎますが、私のライフワークであるお料理で命を養う、心と身体が整う料理は、決して「美味しい」を目指しているわけではないということを再認識しました。久々に母がお寺の台所に立ってくれて、それを嬉しく眺めていたら「おいしい、と言ってもらうこと」が嬉しいのだと言っていました。「ハテ、私はどうだろう?」そこから「?」が始まっていたのだと思います。
実に6年ぶりの開山忌のおふるまいでした。今回は三好典座和尚様に御来山頂き、直々に修行道場で腕を振るわれたご様子を拝見いたしました。一緒に同じ厨房に立つことができたことは光栄としか言いようがなく、恐れ多い気持ちの方が強く調理に入るまでは不安しかありませんでした。ところが献立の確認をしていただき、買い出しの材料をチエックしていただき、作り進めてゆくうちに、ほんの一瞬気のせいかと思うほどの瞬間でしたが、方丈様の中に修行道場で光らせていたであろう眼差しを見て安心しました。典座和尚様にとってはどこにおられても同じことなのだとわかったからです。今年は方丈さんの修業仲間の三宝寺様の奥様である、ともちゃんも手伝いに来てくれて大変助かりました。彼女のInstagramには、ほぼリアルタイムでの開山忌がアップされていますからぜひご覧ください。
@sanbouji_official
三好典座和尚様の仕立てるお料理は、どれも美味しいと思いました。滋味のある、やさしい調和した料理でした。一緒に厨房でお仕事をさせていただいた後の今ではご著作の手元の写真が立体的に見える、という不思議を味わっています。私は「おいしい料理」を作ることができるのだろうか。もうしばらくこの問いへの答えは自問自答してみようと思います。「私は美味しい料理をつくりたいのかどうか」と変換してみてもよいかもしれません。みなさまはいかがですか?美味しい料理って、何でしょう?
2024.10.25 台所手帖
失敗は成功のもと

池坊のお華の先生のお宅で、少々季節外れの風船カズラが花をつけて揺れていました。とても可憐で儚げながら小さな白い花と緑の繊細な風船が印象的でついつい目にすると顔がほころびます。そういう草花の存在に幸せを感じます。どなたでも、笑顔で対応してくださるとうれしいなと思う、それに近いと感じた今日この頃です。急に朝晩冷え込みあっという間に冬かと思えば日中は夏日。着衣に迷っております。
以前に教えて頂いた赤ずいきの汁を作りましょうと、里芋人参大根などを煮込んで、うっかり赤ずいきを刻んで入れてしまいました。途中からおっと、と気づいて皮をむき刻んで(本当は湯通しして絞るなあ、、)と思いながらなんとかなるか、と料理を続行してしまいました。味噌を溶いていただいていると、「なんだか舌がピリピリする!」と食べた皆がいいだしました。実際、これはシュウ酸カルシウムの仕業、赤ずいきのあく抜きをしっかりしなかったことが原因でした。シュウ酸カルシウムの結晶は四角だか三角だかに尖っていて、そのとんがりが口内を刺激していたのでした。料理はやはり、必要な手順をしっかり踏まえなければならない、ということですね。そのあと、ひと鍋の汁をどうしたかというと、いったんピリピリのアクの溶け込んだ汁を洗い流して、新しく出汁を足したのでした。久々の大失敗でした。
〈きくらげL I F E〉
9月に、天徳寺典座寮にて撮影協力をさせていただきました。菌塵研究所のスタッフさんのもえちゃんとは、京都で入門した薬膳教室の先輩後輩、いつか何かを一緒にしたいね!といっていました。だんご汁を一緒に作ったり味噌づくりの会に誘ってもらったり、薬膳料理の会に誘ってくれたり、松露やきのこについていろんなことを教えてくれるきのこの達人です。
1年分の季節を1日で撮るという、プロの撮影現場に真剣勝負。料理の出来栄えは、さて、Instagramにてお楽しみに。
@kikurage_life
撮影は道環の写真でおなじみの僕ら、の藤田さん。日々是修行、お料理の研究、修行します。
2024.08.10 台所手帖
夏のごはん

みなさまいかがお過ごしですか?山河草木のうつろいは、正直ですね。芽吹いた緑があっという間に濃くなって、お寺の裏の山も青々と茂っています。あまりに気温の高い日には木々の枝葉が裏返って逆立ち、白色系茶色緑に見えるような時があります。雨風の被害が広がらず、動物と人とのバランスが保たれますように。
地球環境を心配する当の私はといえば、規則正しく過ごしたいのに仕事の段取りをうまく組めずに悪戦苦闘しています。そうすると身体が定期的に悲鳴を上げます。心身ともに滞りをなくして、気血の流れがうまく巡るように暮らしたいものです。
元気が足りない時には、季節の野菜ご飯がいいですね。空豆、インゲン豆美味しく頂きました。いまは、胡瓜、トマト、甘長唐辛子、ピーマン、西瓜、そしてトウモロコシの出番です。皆さんは、トウモロコシはどのように召し上がりますか?塩ゆでが多いかも知れませんね。蒸し器で蒸したり、グリルで焼いたり、天ぷらなどという場合もあると思います。手の込んだところでは、コーンスープでしょうか。子供の頃は祖母や母が作ってくれるコーンスープが楽しみでした。トウモロコシの皮を剥くお手伝いをしていましたが、それがとても大変な作業だったような記憶があります。けれど、それは自分が小さかったから。トウモロコシを剥く時は「あの頃」に一瞬戻れる楽しいひと時です。近頃は、茶色くなったトウモロコシのヒゲの先っちょをハサミでちょきんと切って皮を剥きながら、きれいな翡翠色のひげをつかんで纏めて引っ張り、そのひげも大切に使います。ひげは玉米鬚(ぎょくべいしゅ)とか南蛮毛という漢方薬です。車前草(オオバコ)や冬瓜皮などと一緒に煎じて、むくみ取りに使われます。芯は「玉米軸」といい、簡単にいえば、どれも身体の熱を冷ましたり余分な水分を出したりする働きがあるのです。
トウモロコシはもともとは南米原産で、栽培の歴史は、マヤ、アステカ古代文明にまで遡れるそうです。15世紀末にコロンブスによってヨーロッパに伝わり、ポルトガル人によってジャワに導入、16世紀ごろ中国に伝わり同時に日本にも伝えられたという説が有力です。「トウモロコシ」の品種は様々で甘みの少ない乾燥させて穀物として利用するものと、乾燥させずに生を加熱して食べる甘みの強いものがあります。日本では「甜質型」(スイートコーン)が多く栽培されていますが、中国では甘みのない「硬粒種」も製粉してマントウや粥にするそうです。トウモロコシ粉に山薬(山芋)を3:2でお粥にすると玉米山薬粥。話が逸れましたが、トウモロコシご飯をご紹介します。
【トウモロコシご飯の作り方】
トウモロコシ1本、給水させたお米3合、塩小さじ1を鍋に入れ炊きます。
炊き上がったらトウモロコシを芯から外し混ぜます。大葉青紫蘇があれば刻んで混ぜ込みます。
トマトの味噌汁とトウモロコシご飯に胡瓜の糠漬け、枇杷。是非やってみてください。
毎日のご飯で体調を整えることが出来たら何よりですね。ご無事に夏を乗り切りましょう。
