読む
2025.08.08 台所手帖
きくらげと金針菜

金針菜と木耳きくらげは、大変相性がよい。炒め物でよく見かける。
薬膳料理、といえば近頃よく耳にする医食同源のいたわり料理だ。食養生のことでもあり、食べることで体調のバランスを整えて心とからだを養う料理のことをさす。
美味しくないけど体に良い料理でしょ、とか苦いの?とか、特別の食材が要る料理なの?という少しややこしい先入観は、随分薄れていると思う。それくらい今の生活には「薬膳」という言葉が浸透してきている。健康でいられる時間は少しでも長い方がいいから、食養生について興味を持つ人も増えているからだろう。
基本的なことは分かりやすくいろんなメディアや本、雑誌が解説してくれている。手軽に生活に取り入れられるし、試してみるとちょっとした不調の原因が判明して身体が軽くなる場合があるだろう。そうすれば気持ちも楽になり、生活することも楽しくなるかも知れない。薬膳は中国の伝統医学の基礎理論がもとになっているが、決して過去の遺産ではなく、それが現代の私たちの生活にも当てはまるという壮大な理論体系だ。縦長の島国の気候風土に根づいた民族でも一様ではない体質を、分析し調整する知恵の集積で「独自の、とか渡来の、」を越えた英知だと思う。今、その知恵に触れることができると考えただけでワクワクする。薬草はずっと人々の病を癒し、心をやすらかにしてきた。山野に実る恵は私たちを生かしてくれた。そう考えると、大地と海、山、空があり、季節があること、それを感じる自分があることに感謝でいっぱいになる。
調子が悪い、と感じる時は症状だけを見るのではなく、その症状のもと、原因に向き合うことが大切。きれいな空を見て、美味しい空気を吸って、湧き出る水を飲んでほしい。もちろん、季節を正しく楽しく凌ぐ必要もある。少し気を付けるだけで心と體が楽になる知恵があるなら、みなさんと共有してゆきたいと思う。
日本の発酵文化もしっかり見直されていて、若くて子育て奮闘中のママ達の世間話に「麹が好きで、塩こうじや醤油麹を自分で仕込んで使っている、甘酒も自分でつくる」と聞いて、はじけるような若さと美しさより、その食に対しての意識の高さにびっくりしたことがある。とても嬉しいと思った。街中で暮らす孫が、おばあちゃんの料理が美味しいといって昔献立を好んで食べに来る、という話も大好きなエピソードだ。私も、今は昔献立を習うことが楽しくて仕方がない。たいてい旬の野菜をどう保存するか、が料理のもとになっているように思う。
ニキビが出始めた若い子が食生活を見直し、自分の身体に意識が向いて自分が体に取り込む物の成分表示を気にし始めるとしたら、それも素晴らしいと思った。自分の心と體を知ることができたらよりよく過ごすことができる。健康、万全でいることはとてもありがたいこと。
結局「食べたもの」で「体はつくられる」のだ。ジャンクフードがダメというのではない。ちょっと減らして、そのぶんの予算でいい油を調達してほしい。少しの塩を振った野菜を炒めるだけで素晴らしい一皿ができるから。
できれば大手の油メーカのものではなく、単価は高くても丁寧に絞られたなたね油やこめ油、ごま油を使ってみてほしい。かるく熱して、ゆでたきくらげと金針菜を炒めてみよう。金針菜でなくてもアスパラやきのこでもよい。アスパラは食感が似ている。金針菜は乾燥のものが割と手軽に手に入るので水に戻して茹でて使うとよい。私は住空間の横の小さな畑で金針菜を育てて何年かになるが、それなりの収量を得られるようになった。やっと細々とお裾分けができるようになった。薬膳の師匠にノカンゾウとヤブカンゾウ、どちらでも食べられるのかをお伺いしてみたら、どちらも食用になるとのことだった。よく見てみると、一重のノカンゾウも八重のヤブカンゾウも季節になるとあちこちに咲いている。しかし、ちゃんと茹でて水に晒さないとおなかを下す可能性があるので注意は必要だ。食材の薬効を活用する場合と、不要に摂ってしまわないように抜く(アク抜きともいう)「その技術」も、また「料理」ともいうのかもしれないなぁと、ちょっと思った。
作り方
1.乾燥木耳は水で戻し刻む。生木耳ならそのまま刻んで茹でる。
2.金針菜はゆでて水にさらし、炒めて、塩コショウを振る。
あとはご飯と味噌汁、塩もみキャベツと粉ふき芋、とか、焼き油揚げか豆腐、梅干か佃煮干し椎茸、塩もみ小松菜などがあればいい。
☆木耳(きくらげ)について
「きくらげ」には「きくらげ」と「あらげきくらげ」がある。
「きくらげ」=「黒きくらげ」
「あらげきくらげ」=「裏白きくらげ」
大型で裏側が白い毛で覆われている。分類学名は明らかに違う。流通しているのはあらげきくらげが多いようだ。黒木耳は本来珍しいのかもしれない、ということを密かに記しておこう。
効能は
補益気血 滋補強壮 滋補肝腎 潤肺止咳
清熱(涼血止血) 活血(活血散瘀) 解毒(抗癌) 瀉下(潤燥利腸)
まとめて簡単にいえば
ミネラルが多いので血液を増やし、気を補い肺を潤す。空咳や口の渇き乾燥肌の改善にも有効。
すばらしい薬効のある食材。腎と肝を補う。どの年代にも必要。ビタミンDも豊富背が伸びる。
☆金針菜について
ススキノ科ワスレ草属
中国名 金針菜、黄花菜 萱草花 安神菜 忘憂草
和名 ノカンゾウ ヤブカンゾウ ユウスゲ 山菜の萱草。効能は「萱草嫩苗」のこと
日本では山菜として若苗、若芽を食用
分類学名は同じだか、種類がいくつかあり一重か八重か日本国内でもノカンゾウとヤブカンゾウの違いがある。どちらも食してみたがあまり違いは分からなかった。
効能は
清熱 清熱解毒 清熱利湿
理気(解鬱) 補血
まとめて簡単にいえば
体のほてりをとり、気、血を補い体内を巡らせる力がある。鉄分はほうれん草の数倍(20倍?!)
*Instagramをはじめた。まだ、あと1年は準備期間中。
*スタッフさんと試行錯誤しながら山の麓に畑を始めた。畑の師匠が沢山いてくださるのが心強い。
*薬膳精進料理のご提供は随時受付中。
*季節の養生講座を試験的に開催。鍼灸師の先生と協力して運営中。
次回は「秋の土用のセルフ灸 (仮)」
お問い合わせはHP、天月草木舎のInstagramよりお待ちしています。
皆さんの心と體を整えるお力添えになれば幸いです。
2025.05.30 お悩み相談
【質問】仕事が落ち着いた今、先の見据え方が見つけられません
【質問】
仕事上で大きな目標を追いかけて働いていましたが、この歳になり、自分の毎日を顧みたときに、ふと「なんのためにここまで頑張っているのか」がわからなくなる瞬間があります。体力的な衰えなのか、子育てもある程度落ち着いた環境の変化なのか。はたまたそれとも違うものか、分かりませんが、疲労感や虚無感を感じ、これから先をどのように見据えたら良いか考えてしまいます。
【回答】
ご質問ありがとうございます。なるほど、これまでの仕事への熱意がなくなり、日々のはしばしに疲労感や虚無感を感じてしまう、ということですね。質問者さんは私と同世代でいらっしゃいますね。お気持ちよくわかります。
おそらく質問者さんは、人生を終点のほうから考え始められたのではないでしょうか。それまでは、誕生から子供へ大人へと、順を追った成長のなかで見ておられたご自身の人生を、あるときから不意に、逆から見られるようになったのでしょう。地位や富や名声をより多く得ていくことが人生の成功者であると思っていられたときとは逆に、自分がいくつで亡くなるか、体はいつまで動くか、それならばあと何年しかなくて、そのあいだ自分はどうしようかと、ご自身の人生を終点から見るようになると、地位や富や名声なども色あせて見え、こうしたことを追求して生きることが、なんとも空しくなってしまったのではないでしょうか。 これは一見無気力になってしまったように見えますが、実はよろこばしい変化とも言えます。それは質問者さんが、ご自分の生を生きることの真実に直面したということだからです。
私たちが生きることとは、自分の固有の体・こころ・歴史をもった人生をどう生きるかを追求することであり、それには、自分とはどのような生を歩み、どのような性格で、なにを行い、社会にどのように還元するかを考えることが必要です。その際、もっとも重要なのは、地位や富や名声の多寡でもって他人と比べながら評価するのではなく、外部的な評価軸に頼らないで自分を見るようにすることです。
そのうえで、やりたいこと、やるべきことを決めるのです。こうしたことを決めるときに、欲求からではなく、むしろ周りや社会に対してどのような奉仕ができるか、という点で考えるべきです。50年以上も社会に守られて受けてきた恩恵を、社会に対してどのように返すか、なにが返せるかという点を考えていかれれば、これからの人生を生きる新たな生き方が見えてくるのではないか、と思います。
こうしたご自身の生き方を見つめるとき、質問者さんは実は、仏教の教えに近づいているともいえます。ご自分のこれからの生き方を振り返る過程で、最初期のお経の一つである、中村元訳『真理のことば・感興のことば』(岩波文庫)をぜひ手にとってみてください。お釈迦さまが非常にわかりやすく示してくださっているお言葉に、いまの質問者さんに必要なことがらが見つかるのではないかと思っています。
2025.04.30 住職のおすすめ本
大澤真幸『我々の使者と未来の他者』 (集英社2024)
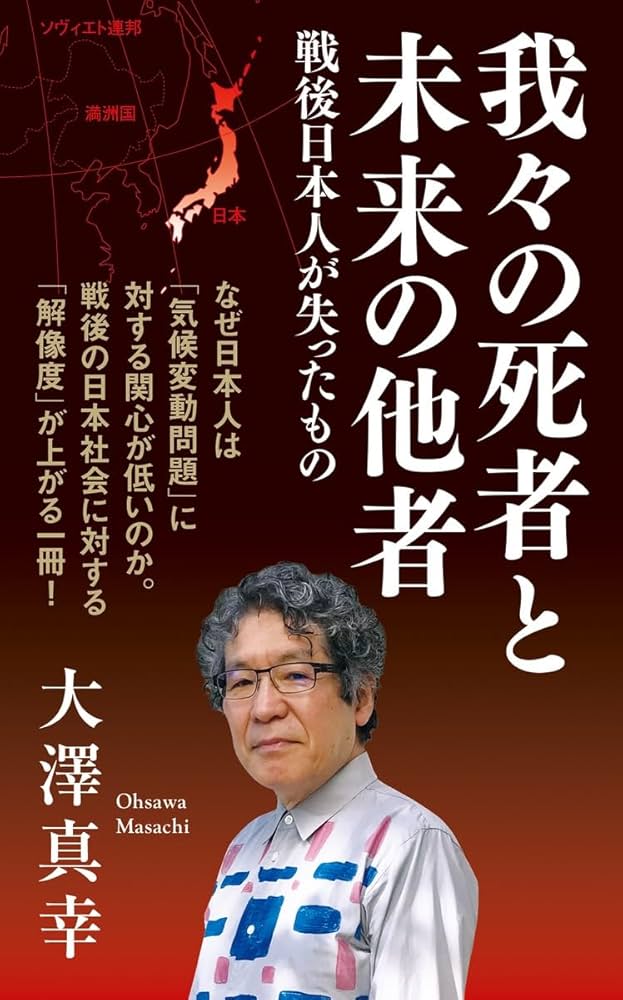
お墓を上げてしまい、御遺骨は永代供養塔に入れたい、と希望する檀家さんが増えている。これは全国的な風潮であり、これからも進んでいくように見える。次の代がいないので永代供養を希望される場合はわかるのだが、疑問なのは、子供さんがいらっしゃるのに永代供養を希望される場合である。その理由をお訊ねすると、「子供に迷惑をかけたくないから」と言われる。お墓を持つことは迷惑なのか、お寺とのかかわりを持つことは重荷なのか。お墓も仏壇も、先祖からの遺産である。それを重荷と思い、継承せず、自分のところで断絶させたいと願っているように見える。これは大きな絶望であるといえる。なにに絶望しているのか。これは、この檀家さんの件だけではなく、私たち現代の日本人がなにに絶望しているのか、という問題でもある。
大澤は本書でこの疑問に答えようとしている。大澤によれば、現代日本人が失ったのは「我々の死者」である。第二次大戦の敗戦後、日本人は、それまでの軍国主義はまちがいであるとして、大戦で死亡した膨大な数の戦死者を、「我々の死者」として祀れなくなった。戦死者たちの希望を、今の私たちの希望として引き継ぐことを断念した。この喪失が、「未来の他者」への想像や責任の欠落や喪失として現象する。なぜなら、自分たちを過去の死者からの継承者としない場合には、自分たちの継承者としての未来の他者も、想像できなくなるからである。それは現代日本において、環境問題において、あるいは原発の問題において、未来のまだ見ぬ子供たち(「未来の他者」)へ渡す責任感を喪失し、無関心になることに帰着する、と大澤は言う。なるほどと思う。では、どうすればよいか。どうすればわれわれは、「我々の死者」を見出し、「未来の他者」への責任を回復することができるか。
お寺側から言えば、葬儀や法事の際、いったいこれはどういう行為であるのかを見つめることが必要だと思う。葬儀や法事とは、いわば臨終のときを追体験するということである。臨終のとき、人は、残る人々に、なにかを渡す。それは、希望や願望であるだろうし、あるいは恨みや心残り、苦しみなどの暗い感情かもしれない。しかしともあれ、見送りの人に対して、なにかを託すのである。その託されたものを思い起こし、それをわれわれへの希望や願いに変えてあらためて受け取ることこそが、葬儀や法事を営むことの本質である。
そして、その受け取ったことを次の代に渡すことが、葬儀や法事のもう一つの役割でもある。だから、小さな子供を抱えて葬儀や法事に出ることは正しいし、故人の思い出の片々を会葬者が語り合うことは正しい。そのことが故人を「我々の死者」にし、私たちがそこに接続し、未来への責任を持つことになるからだ。本書は今の時代を読む、大事なプラットフォームとなる一冊だと思う。
2025.03.30 お悩み相談
【質問】進路について悩んでいます
【質問】
将来やりたいことがわかりません。それでも、文系や理系を選択したり、大人に近づくにつれて方向性を決めなければいけません。どのように決めていけば良いのでしょうか?
【回答】
ご質問ありがとうございます。質問者さんは10代の学生さんでいらっしゃるのですね。将来について、そんなにはっきりとしたビジョンなんかまだ持てないのに、文系か理系か、その他もろもろについて、周りは自分にどう生きるかを迫ってくる。どうしたらいいのか、というお悩みですね。なにやってもいいぞ、と言われるとかえって困ってしまいますよね。
私のことを言って恐縮ですが、私は将来やりたいことの前に、将来やらなければならないことがあった人間でした。お寺の子どもとして生まれたので、お寺を継ぐということが、目の前の義務としてあったのです。ちょうど相談者さんと正反対の状況であったわけです。やりたいことがわからず苦しい、ということはなかった半面、義務としての生き方が迫ってくる重圧をどうするかを考える毎日でした。義務から逃げることも考えましたが、逃げてもうまく生きられるようには思えませんでした。いろいろ考えた結果、義務つまりお寺の住職としてお坊さんをしながら、しかも同時に自分のやりたいことを探ることになりました。私は本を読み、それに対して考えたことを書き記すということをずっとやってきたので、こうしたことならお坊さんをしながらもできるのではないかと思いました。つまり、私の場合、やるべきことに沿うようにやりたいことを見つけ出したわけです。この方法はわりと成功していて、私はいまも、お寺の住職の義務感だけに押しつぶされることもなく、また自分の自由だけを身勝手に追求することでもなく、両方のバランスを取って生活でき、充実した人生を送れています。
私たちは、それぞれ異なった肉体的・心理的・社会的条件のもとに生まれます。その条件を重ねて見た時に、自分がすべきことが見える場合があります。ただしそれは、すべきことであって、したいことではありません。すべきことは、つらく、苦しく、したいことは、うれしく、面白い。私たちには、このどちらもが必要です。この両者のバランスを取ることが大事だということです。質問者さんの肉体的・心理的・社会的条件をご自分で少し客観的に見つめてみると、ご自分のやるべきことが見えてくるかもしれません。それは一種の義務であり、拘束です。それを破ったりズラしたりしたところに、多分あなたのやりたいことがあると思います。そしてここは大事な所ですが、やりたいことは、案外、やるべきことのすぐそばにあるものなのです。まずはやるべきことを探し、それを少しズラしてやりたいことを見つけてみてください。二つのバランスがうまくとれたときに、あなたらしい人生があると思うのです。ぜひあなただけの充実した人生を送ってください。
2025.03.30 住職のおすすめ本
一橋大学社会学部 加藤圭木ゼミナール編『大学生が推す 深掘りソウルガイド』 (大月書店2024)
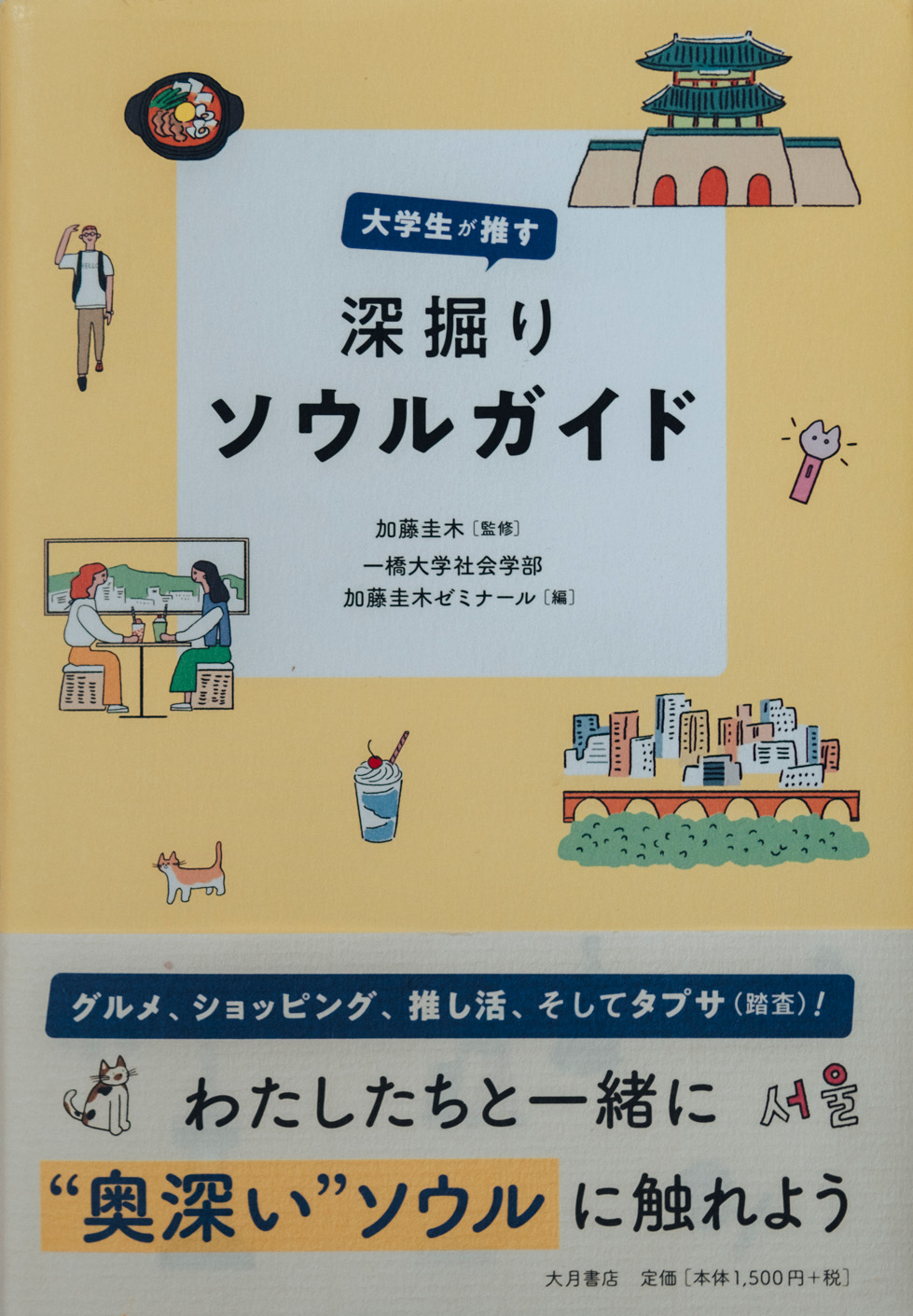
こんな想像をしてみよう。現在私たちが住んでいる国が、かつては別の国に占領されていて、その痕跡が、町のすみずみ、かどかどにいまも残っているとしたら。そしてそれを毎日毎日私たちが目にせざるをえないとしたら。私たちはきっと、この別の国に対して、根強い感情を持つだろう。それが、怒りであるか、憧れであるか、悲しみであるか、あるいはそのすべてであるのかはわからない。ともかくも、根強い感情をつねに掻き立てられるだろうということは、容易に想像できる。これは現在の韓国と日本との関係であり、あるいはかつての日本とアメリカの関係である。日本は7年間、アメリカを中心とする連合国軍の占領下にあった。その占領の痕跡は意識的に各所で消されたが、日本人の精神性には、アメリカに対する恐怖と憧れとが刻印された。韓国の場合は、日本は36年にわたって占領したため、その痕跡は社会のすみずみに浸透してのこり、いまも日々、韓国の人々の根強い感情を刺激し続けている。私はこのことを本書で教えてもらった。本書は一見、お気軽でおしゃれな、今風のソウルの観光案内、グルメ案内と見える小さなかわいい本でありながら、手に取った者にソウルの重い歴史を手渡してくるものだ。たとえば、ソウルに行くには仁川(インチョン)国際空港が便利だが、この空港が存在するのは、江華島の向かい、そのすぐ近くである。1875年の江華島事件こそが、日本の朝鮮半島への軍事行動のはじまりであることは日本人は歴史の教科書で知っている。
だが、仁川空港に乗り降りする多くの日本人のうち、いったいどれくらいが、その歴史に思いをはせるだろう。思い出そうが出すまいが、その歴史的事実は厳然としてその場所にうずくまっている。それに気づくことは、加害国としての歴史に気が付くことであり、韓国を絶えず刺激しつづける傷のありかを自覚することだ。しかし、この傷のありかを自覚することではじめて、私たちは対話のいとぐちをかすかに見つけられるのだと思う。これは韓国に対してだけではない。ヒロシマ、ナガサキにおけるアメリカ、南京における日本、フクシマにおける東京電力において、傷のありかを自覚することで、私たちは、困難な対話のいとぐちを見つけられると信じる。
